「ここが御歳市ね」
終着駅である御歳駅の改札を抜けた彼女は、ぽつりとこぼした。当然彼女の言葉に反応を示す人などいるわけもなく、口の端からこぼれ出た呟きは、冬特有のピンと張りつめた空気を無意味に揺らめかせただけだった。
『御歳市』
面積約60㎢。人口約三万人。経済状態はあまり芳しくはない。市としては全国の中でも小さい部類に入るが、歴史の古い町であり、一般的に古墳時代と呼ばれるころには既に文献にミトセの名が記されている。御歳市の西方に鎮座する御歳山は、その地方では霊山として知られており、数多の伝説も残されている。
目を落としたのは御歳市の簡単な説明。しかし、はっきり言ってこれだけでは必要なことは何も分からない。いつものことながら、もともと理解させるつもりもないのかもしれない。そう結論を出した彼女は、説明ページを読むことをやめ、御歳市の地図が印刷されたページを広げる。
町の地理を把握するためには歩くのが一番手っ取り早いと考えている彼女は、プリントされた地図を片手に足をふみだした。今回の指令では、市内のほぼ中心地域が彼女の活動地域になると予想されているらしい。予想されている地域だけは、市内の他の地域よりも詳しい地図が載っている。
「………」
今回で一体何度目になるのだろう?
いくら任務をこなしても更なる任務の数は増える一方で、それに比例して組織と一般人の被害も増えていく。はっきり言ってしまえば、最終目的の遂行なんておこがましくて口に出せないような状態。
けれども、彼女は歩みを止めない。この内なる想いが身を焦がしつくそうとも……。
「―――そう。この世界から存在を抹消するまで」
彼女はその手に大鎌を握る。
目の前には影が五つ。
さっそくお出ましとは、運がいいのか悪いのか。いずれにしても、日頃の行いの賜物には違いない。
白い制服に身を包み、高い位置で束ねた腰まで届きそうな黒髪を風になびかせ、彼女は尊大に、あるいは傲岸に、ソレらを睥睨する。そして、その手に握る大鎌の刃を青白い月光の下にさらし、いつものように謳いあげる。
「わたしは『血塗れの処女(デス・エンジェル)』の名を冠する者。紅蓮の意思を宿す者。その名と意思もて、破滅の救済者として君臨する。悪夢(ユメ)の深淵から出でし亡者よ。わたしの悪夢が汝らを断罪する」
五つの影に彼女の声は聞こえていない。しかし彼女は言葉を紡ぐ。自らの思いをより強固にするために。
影はゆらゆらと上半身を揺らしながら近づいてくる。まだ染まりきっていないのだろう。今ならいくら数がいても万が一すら起こらない。
影は一直線に向かってくる。彼女は右前方へ――影の集団の左側に回り込むように跳ね、着地と同時に左回りに身体を捻る。
「やっ!!」
吐き出した息とともに大鎌を薙ぐ。夜の闇よりも、なお黒く昏い刃が勢いよく影を切り裂いていく。
影が一つ切り捨てられたことで身近に迫る危険をようやく悟ったのか、残りの影が一斉に彼女を見る。緩慢な動作は相変わらずだが、自衛のために向かってくる。しかし、彼女にはわざわざやられてあげる義務も理由もなかった。
地面を勢いよく蹴り、低姿勢で影の懐までもぐりこむ。その勢いのまま一つ押し倒し、他の三つの影に狙いを定めて大鎌を振るう。次いで、押し倒した影の一部分――人間なら首にあたるであろう部分――を柄の先で一切の躊躇なしに突いた。
「五体相手に30秒。少し鈍り気味かしらね」
呟いたときには既に大鎌はその手にはない。同じく、彼女の呟きを耳にする者も、この世界にはやっぱりいなかった。それが、開始の合図になっていたにも関わらず。
御歳市の夜は、まだ始まったばかり―――。
†
「それじゃ、また明日。学校でな」
「ん。また明日」
退屈な進学塾での時間を過ごし終えた俺は、いつも通り友達と互いに別れを告げて帰途についた。
「それにしても、受験まであと一年ないんだよなぁ」
今は二月。一学年上の先輩たちの中には、既に大学合格を決めている人も多い。もちろん、後期試験を受験する先輩たちにはあと少しの期間があるが。
一年も経たないうちに俺たちも同じ立場になるのだが、いかんせん今は実感が湧かない。
(ま、あと一年あるしな)
という考えが強いからだった。それでも、確実に近づいてはいる。テストの点数や偏差値が上がった下がったで一喜一憂し、模試の判定次第では自殺者が出ることもある。つい昨日だって、『東大志望の受験生、判定が落ちたことを苦に自殺』なんて見出しが新聞の片隅に載っていた。
人の死を笑い物にするつもりは毛頭ないけど、A判定からB判定に落ちたくらいで自殺するのはどうかと思う。合格率はそれでも60パーセントくらいはあるだろうし、本番はまだ先だ。今死んだら挽回だってできないのに。
「ヤな世界だよ……」
この年齢を通り越して行った人たちのうち、おおよそ誰もが考えたであろうことを考えながら、空を見上げた。
夜空には満月、と呼ぶまでには至らないが、それでも円い月が静かに儚く、しかし煌々とその存在を示している。
「久々に綺麗な夜空だし。アーケードをくぐって帰るんじゃもったいないよな」
俺は呟きと同時に、いつもとは違う道に足を向けた。
「この通りってこんなに暗かったっけ?」
ひさしぶりに通る道に抱いた感想は、そんなことだった。いつもはあまり使わない道だが、何年も使っていないわけじゃない。今日みたいに月が綺麗だったり、星が綺麗だったりする夜にはこの道を通っている。そんなわけだから、俺が抱いた感想はこの近辺に住まうすべての人が感じているだろう。
…………と、そこまで考えてふと、奇妙なことに気がついた。
確かに夜も遅い時間だが、日付が変わるまでにはまだ一時間以上ある。要するに、今は頑張って一日働いた人たちの帰宅時間範囲に当てはまるのだ。そんな時間なのに、塾で言葉を交わした友人以降、人を見かけていない。
「珍しいな」
という感想も、10人いれば8人くらいは納得してくれるだろう。
が、それは見かけないのが人間だけであった場合に限り、である。
いつもなら路地裏で会議を開いているはずの猫たちも、電線に並んでいる鳥たちもいない。それどころか自動車の排気音、テレビの音、一家団欒の声、果ては犬の鳴き声すら聞こえてこない。
「……変、だよな」
そう呟いたのは、塾から家までの道程のちょうど半分というところだった。この状態は明らかにおかしい。異常と言ってしまってもいいくらいだ。
なぜなら、『暗』いのではなく『昏』かったのだ。そう、この道を歩き始めたときからずっと。民家の明かりが点いてないだとか、街灯が少ないからといった暗さではない。町の空気だとか、雰囲気だとか、そういったものが昏いのだ。例えるなら、光の届かない深海。あるいは澱んだ沼。
いや、それよりも……。
「あれで終わりかと思いきや、まだ残ってたのね。それも本命が」
唐突に、目の前の闇から声が発せられた。ひどく透き通っている声質に似合わず、そこに乗せられた感情は周囲の物を総て焼き尽くすかのような怒りだった。
コツッ。闇の中に足音が響く
――それは今から死ぬ者への手向けの鐘の音に似て――
コツッ。闇の内より己が身を浮かび上がらせ
――それは聖母にも死神にも見え――
コツッ。獲物を見つけた肉食獣の如く
――それは裁断者のように――
コツッ。双眸には爛々たる光が揺らめいて
――それは怜悧なる意思で――
コツッ。死神の大鎌を月光にさらしていた
――それは託宣を歌い上げた――
「愚者には死を」

どう見たって命を狙われているのは俺なのに、自分のことだと理解できてない。
ただ、ひどく綺麗だと、そう思った。
「今から死ぬというのに、随分落ち着いてるのね」
その言の葉には感心か、呆れか、あるいはそのどちらも内包していたのかもしれない。
とはいえその言葉で我に返った俺は、間抜けもいいところだろう。自分の命が狙われているのに、狙っている相手に対して綺麗だ、なんて。
「それとも諦めたのかしら?」
言いつつ、手に持った大鎌を構える。込められた殺意が明確な質量を持って圧し掛かってくるようにも感じた。
「……ひ、人違いじゃないのか?」
何とか発した言葉は滑稽なほど震え、自分のものとは思えないほどかすれていた。
俺は今まで普通に生きてきた。両親を亡くしたりと多少不幸が勝っている気がしないでもないが、それでも命を狙われるようなことはしてこなかったと自負している。
「ここに存在しているということ。そして言葉を発しているということ。それが、あなたがわたしに殺されるに値する何よりの証拠よ」
しかし彼女は眉一つ動かさずに言いきった。お前の存在自体が罪だと。お前はわたしに殺されるべきなのだと。
彼女の重心がすっと落ちる。
地面を蹴る音が耳に届いたときには、命を刈り取らんとする大鎌が目前に迫っていた。
ブオォォオン!
獣の咆哮を想起させるような風切り音を伴って、大鎌が頭上を通り過ぎて行く。無意識のうちに、右手で首を押さえていた。ドクドクと早鐘のように鳴る鼓動。それが、まだ俺が生きていることを教えてくれた。
当然避けたなんて上等なものじゃない。恐怖で足が後退してつまずいただけだ。助かったのは本当に運が良かったとしか言いようがない。
「運がいいわね。けれど、次はないわ」
言いつつ、半身になり大鎌を構えなおす。
その二撃目が繰り出される前に、俺は走り出した。後ろではなく、相手に向かって。彼女は虚を突かれて反応が遅れる。
それは人間なら当たり前の反応。誰しも、自分から死に飛び込んで行く酔狂な人間がいるとは考えにくい。この思考の埒外の事態でまず一瞬。ましてや彼女の場合、背を向けて逃げる獲物を狩るために、重心が前に傾いていた。俺の一歩目と彼女の一歩目が別方向に踏み出されたことでさらに一瞬。合わせて二瞬。それだけあれば、眼前に迫っていた死から逃げるだけなら十分!
俺は勢いを殺さずに無我夢中で走り続ける。当然彼女も追ってきているのだろう。背中越しに鋭い殺気を感じる。立ち止まったら確実に殺される。死にたくないと、ただそれだけを思いながら闇の中をひた走った。
「はぁ……はぁ…………はぁ……はぁ……ゲホッ……ゲホ」
どれくらい走ったのかも、どう走ったのかも分からなくなったころに、俺はやっと我が家へたどり着いた。あの物騒な大鎌女が諦めたとは考えづらいが、追ってくる殺気はもう感じなかった。
「はぁ……はぁ……も…………ダメ、だ」
身体中が急な酷使に耐えかねて悲鳴を上げている。座り込んで玄関の扉に背を預け、荒い呼吸を繰り返す。
もう一歩どころか、指一本動かしたくない……。
しかし、屋外にいつまでもいるわけにはいかない。今の状態じゃ見つけられることが即、死に繋がる。ここまで逃げてきて、そんなことは絶対にゴメンだ。
重い身体を引きずって、俺は玄関の扉を開けた。
「…………ただいま」
「お兄ちゃん! 心配したじゃない!」
家に入った俺を出迎えたのは、妹である美咲(ミサキ)の怒声だった。パジャマ姿で腰に手を当て、仁王立ちといった感じだ。風呂から上がってさほど時間が経ってないのか、肩付近できれいに揃えられた髪が少し濡れていた。
まぁ、心配されるのも仕方ない。あれだけ逃げ続けてれば否応なしに余計な時間がかかっただろう。
「悪い悪い。ちょっと本屋に寄り道してたからな」
平静を装いながら俺は、壁に掛けてある時計に目を向けた。いつもの帰宅時間は22時前後で、今は23時。一時間くらいならなんとかこれでごまかせるはず……。ただでさえ俺のことになると心配メーターの針が振り切れぎみなのに「殺されかけたから遅かった」なんて言おうものなら、それこそ卒倒しかねない…………っていうか確実にするな。うん。
「それならそれで連絡してくれればいいのに……。お兄ちゃんっていつもそうだよね。突然の思いつきで行動するときは一言も言ってくれないし。この前聡さんのところでご飯頂いたときもそう。わたしがせっかく用意してたのに、何の連絡もしないで。それで遅くに帰ってきたと思ったら食べてきた、って。わたしはずっとお兄ちゃんを待ってたのに……。そのせいで周りの人たちがどれだけ迷惑するか分かってるの? きっと分かってないんでしょ。分かってたらいい加減連絡することくらいは覚えるもんね……ってちょっと! お兄ちゃんわたしの話ちゃんと聞いてるの!?」
「聞こえてるよ……」
生きるか死ぬかの寒中マラソンで消費した多大なカロリーを補給しろと脳が急かすので、テーブルの上のおにぎりを口に運びつつ答える。いつもなら美咲の説教モードが始まった時点で自室なり浴室なりに逃げ出すのだが、カロリー補給を優先したせいで逃げる機会を逸してしまった。こうなるともうお手上げである。
けれど、あんな現実離れした出来事を忘れさせてくれるという意味では、これほどありがたいものもなかった。
「聞こえてるならいいけど………………って、いいわけないでしょ!? 人が真剣に話してるんだから、それ相応の態度ってものがあるんじゃない? 聞こえてるじゃなくて、聞いてるじゃないとダメでしょ!! お兄ちゃんのバカ! わたしだっておなか空いてるの我慢してるのに一人で食べだすなんて! それに! ちゃんと「いただきます」って聞いてないんだけど!?」
「当たり前だろ、言ってないんだから。もし美咲が聞いてたらお兄ちゃんは耳鼻科に行くことをオススメするぞ。それともあれか。実は幽霊の声でも聞いたのか? その場合は精神科が第一候補だな。いや、それよりもその前にカルシウムを摂ったほうがいいかもしれないな」
「ど、ど、ど、どこ見て言ってますか!! ちゃんと毎朝しっかり牛乳飲んでるもん!! それでも育たないんだもん!! でもでも、これでもちょっとは大きくなってるんだから!! お兄ちゃんはA だと思ってるかもしれないけど、これでもBなんだからね!! って、妹に何言わせるの!?」
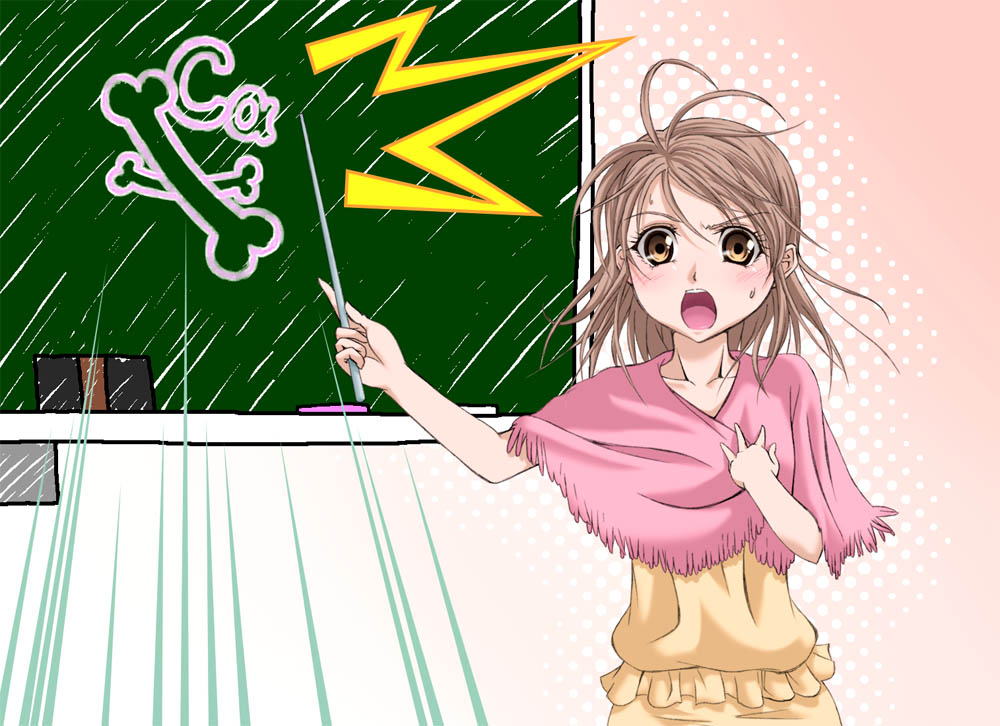
「……いや、俺は別に『どこ』も見てないから。今のは自爆しただけだろ、普通に考えて。だって俺は『カルシウムを摂ったほうがいい』って言っただけじゃないか。牛乳とか言いだしたのは美咲だろ?」
「…………言ってくれるじゃない。それならそれでわたしにも手があるんだから。『One should examine oneself for a very long time before thinking of condemning others.』って、モリエールも言ってるよ? に・い・さ・ん?」
……マズい。美咲がインテリモードに切り替わった。さすがにからかいすぎたか。
美咲は元々頭がいいのだが、テストの点数以外ではそんな部分は微塵も見えない。だが、感情が臨界点を超えると、しばしばこういった風にインテリ面が表れることがある。こうなると口では太刀打ちできなくなってしまう。というより、俺にも一応兄の面子というものがあるので、負けると分かってる戦いはしたくない。……つーか、モリエールって誰だよ。
「悪かった。さすがにからかいすぎた」
「素直でよろしい。さ、ご飯食べよ。おなか空いたよ」
「そうだな」
合わさる手。
「「いただきます」」
重なる声。
そうだ。これが俺の日常だ。あんな訳の分からないことは俺の日常じゃない。もうあんなことは二度とゴメンだ。
Back Next